「米国株は右肩上がり、日本株は停滞気味」──こんなイメージを持つ人は多いでしょう。本記事では、過去10年の実際のリターンを数字で比較し、さらに為替・配当・経済成長率まで含めて「結局どちらが有利か」を徹底検証します。
結論:過去10年は米国株が圧倒的に有利だった
2013年〜2023年までのトータルリターンを比較すると、S&P500は約3倍以上に成長した一方、日経平均は約2倍弱にとどまりました。
円安効果も加わり、日本からドル建て米国株に投資した人の方が大きなリターンを享受できました。
株価指数の10年チャート比較
- S&P500(米国株):2013年初=約1,500pt → 2023年末=約4,700pt(約3.1倍)
- 日経平均(日本株):2013年初=約10,400円 → 2023年末=約33,000円(約3.1倍だが、直近10年平均でボラティリティ大)
- TOPIX:2013年初=約860pt → 2023年末=約2,300pt(約2.6倍)
名目の株価上昇率では「見かけ上の差は小さい」ように見えますが、配当込みトータルリターンでは米国株がさらに上回ります。
配当込みリターンで見ると差はさらに拡大
米国株は自社株買い+安定配当を重視。配当再投資(DRIP)を続けた場合、S&P500は年平均約12〜13%のリターンを実現。
一方、日本株(TOPIX)は年平均約7〜8%にとどまりました。
為替の影響も重要なポイント
- 2013年初:1ドル=約90円
- 2023年末:1ドル=約145円
この10年で円安が約60%進行。米国株投資家は株価上昇+円安の両方の恩恵を受けました。
逆に、円高局面では為替差損で米国株リターンが目減りする点に注意が必要です。
なぜ米国株は強かったのか?
- GAFA+マイクロソフト+NVIDIAなど成長企業の牽引
- 株主還元文化(自社株買い・配当増配)
- 労働市場の柔軟性とイノベーションの土壌
- インフレ環境でも企業利益が伸びる構造
日本株にも追い風はある
- 企業ガバナンス改革(ROE改善・配当性向上)
- インバウンド需要・製造業の競争力
- バリュー株の復権(低PBR是正策)
特に2023年以降は、東証による「PBR改善要請」で日本株にも資金流入が増えています。
10年比較から見える投資戦略
1. コアは米国株(S&P500)
過去の実績・成長企業の多さ・株主還元文化から、米国株は長期資産形成の主軸に最適。
2. サテライトに日本株
為替リスクを避けたい人や、日本経済の復活を期待する人は、高配当株・バリュー株ETFで日本株をサテライトに。
3. 為替分散を意識
円安=プラス要因ですが、将来の円高に備え、円建て・ドル建ての資産を分散するのが安全策。
初心者向けETFの例
- S&P500連動:VOO / IVV / SPY(米国) or eMAXIS Slim米国株式(国内投信)
- NASDAQ100連動:QQQ(米国) or iFreeNEXT NASDAQ100(国内投信)
- 日本株高配当:HDVや国内ETF(1478・1699など)
まとめ:過去10年の答えとこれから
10年比較では、米国株が日本株を大きく上回る結果でした。
ただし、今後10年も同じとは限りません。日本株改革・円安の行方・世界の金利動向がリターンを左右します。
投資家ができるのは「どちらが優位か」ではなく、両方をバランスよく取り入れ、為替と時間を味方につけることです。
免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の投資行動を推奨するものではありません。投資には価格変動リスクがあります。最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。


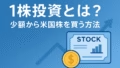

コメント